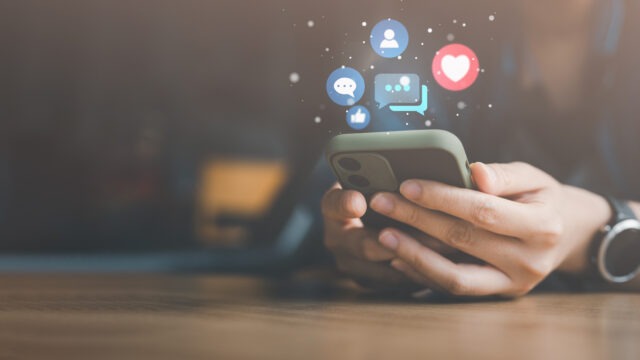このページの目次
1. はじめに:いま注目の「LLMO」とは?

2024年以降、Webマーケティングの世界で急速に注目を集めているキーワードがあります。
それが 「LLMO(Large Language Model Optimization/大規模言語モデル最適化)」 です。
AI検索やChatGPTのような生成AIが主流化し、GoogleやBingもAIによる検索回答(SGE: Search Generative Experience)を導入し始めました。
つまり、これまでの「SEO(検索エンジン最適化)」だけでは、検索結果に表示されにくい時代が到来しているのです。
この新時代の“AI検索対策”こそが「LLMO対策」。
一言で言えば、
“AIに正しく理解され、選ばれるコンテンツ”をつくるための新しい最適化手法
です。
2. なぜいま「LLMO対策」がWebマーケティングのカギになるのか?
とは?Webマーケティングを劇的に変えるAI時代の【必須スキル】を徹底解説!1-scaled.webp)
これまでのSEOは、Googleの検索アルゴリズムを理解し、「キーワード」「内部リンク」「構造化データ」を最適化するものでした。
しかし、生成AIの登場により、検索体験が根本的に変化しています。
2-1. 検索結果が“回答型”に変化した
たとえば、ChatGPT や Gemini に「おすすめのWebマーケティング戦略は?」と聞けば、AIが複数サイトの内容を要約して“答え”を返してくれます。
このとき、AIがどのサイトを参照するかが重要になります。
つまり「AIに理解される文章構造や情報設計」が、これからのSEO=LLMOの要になるのです。
2-2. もはや“人間向けだけの文章”では足りない
従来は「読者にわかりやすく」「キーワードを適切に配置する」だけで良かったSEO。
しかしLLMO時代では、AIがその内容をどう“解釈”するかも意識しなければなりません。
AIは以下のような要素で文章を評価しています。
-
文脈の一貫性
-
ファクトベース(根拠の信頼性)
-
意図・主張の明確さ
-
トピックの網羅性と階層構造
-
外部データとの整合性
これらをすべて踏まえて文章を設計するのが「LLMO対策」の本質です。
つまり、「読者+AIの両方に理解される構造」を意識しなければ、上位表示も、AIの回答引用もされにくくなります。
3. LLMOの基本構造:SEOとの違いを整理しよう
とは?Webマーケティングを劇的に変えるAI時代の【必須スキル】を徹底解説!2-scaled.webp)
| 比較項目 | SEO(検索エンジン最適化) | LLMO(大規模言語モデル最適化) |
|---|---|---|
| 対象 | 検索エンジン(Google等) | 生成AI・大規模言語モデル |
| 目的 | 上位表示・クリック獲得 | AIの回答に引用される/認識される |
| 主要要素 | キーワード・構造化データ | コンテキスト・論理構造・ファクト信頼性 |
| 手法 | HTML最適化・被リンク | 意味論最適化・情報設計・AI評価軸調整 |
| 成果指標 | CTR/PV/CV | AI引用率/生成回答の一貫性 |
簡単に言えば、SEOが“機械に伝えるための最適化”だったのに対し、
LLMOは“AIに理解されるための最適化”です。
4. 【実践】LLMO対策の5つのステップ
とは?Webマーケティングを劇的に変えるAI時代の【必須スキル】を徹底解説!3-scaled.webp)
では実際に、LLMOをどう進めればいいのでしょうか?
ここでは、Webマーケティング担当者が実践できる5ステップを紹介します。
ステップ①:検索ではなく“生成”を意識したキーワード設計
従来のキーワードリサーチは「検索ボリューム」を基準にしていました。
しかし、LLMOでは「AIが理解できるトピック構造」を重視します。
たとえば:
| 従来SEO | LLMO向け対策 |
|---|---|
| 「Webマーケティング 対策」 | 「Webマーケティングとは」「LLMOとは」「AI時代のSEO」など、トピック網羅型構造 |
| キーワード単体で記事を作成 | 意味的に関連するテーマを階層化(エンティティ設計) |
AIは「単語」ではなく「文脈」を読み取ります。
そのため、記事全体をトピックマップ的に構成する必要があります。
ステップ②:構造を“階層的”に整える
AIは「H1→H2→H3」という階層を認識して情報を整理します。
そのため、以下のように明確な段階構造をもつ見出し設計が必須です。
悪い例:
H2: LLMOとは
H2: SEOとAI
H2: 対策方法
(→論理のつながりが曖昧)
良い例:
H2: LLMOとは何か?
H2: なぜ今必要なのか?
H2: LLMO対策を実践する5つの手順
H3: ステップ1〜5
(→AIにも人にも構造が伝わる)
このように、構造を論理的に整理すること自体がAIへの最適化になります。
ステップ③:信頼できるデータを引用する
AIは「信頼できる情報源」を好みます。
信頼性が低い情報は生成時に排除されやすいため、一次情報・公的機関・専門サイトのリンクを必ず入れましょう。
例:
特にLLMO対策では、「どこからの引用か」がAIに明示されていることが評価されます。
ステップ④:E-E-A-TをAIにも伝える
Googleが掲げる評価基準「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」は、AIの学習にも反映されています。
記事内に以下のような要素を入れると、AI理解度が向上します。
-
実体験・データを伴う説明(Experience)
-
専門的知見を示す文(Expertise)
-
執筆者情報・組織名(Authority)
-
出典・参考文献リンク(Trustworthiness)
AIは単なる文章よりも、「誰が、どの根拠で語っているか」を重視します。
これを意識するだけで、AIへの理解精度が飛躍的に上がるのです。
ステップ⑤:AI評価を検証し、PDCAを回す
LLMOは“やって終わり”ではありません。
ChatGPTやPerplexity.ai、Google Geminiなどに自社サイトの内容を質問し、AIがどう回答するかを定期的にチェックしましょう。
もし自社が引用されていなければ、
-
構造が弱い
-
根拠リンクが足りない
-
AIが理解できない文脈
などの問題がある可能性があります。
こうした検証を続けることで、LLMO対策は少しずつ精度が上がっていきます。
5. 自分でやろうとするとハマる「LLMO対策」の落とし穴
とは?Webマーケティングを劇的に変えるAI時代の【必須スキル】を徹底解説!5-scaled.webp)
「なんだ、構造と根拠を整えればいいのか」と思うかもしれません。
しかし、実際に運用してみると多くの企業が壁にぶつかります。
よくある課題:
-
文章構造が複雑で、どこから修正すればいいかわからない
-
AI評価の仕組みが不透明で、検証が難しい
-
Web制作会社やSEO担当と、AI施策担当の認識がズレる
-
E-E-A-Tやトピッククラスタを“形式的”にしか作れない
このように、LLMOは「自分で少し勉強して対応できる」領域を超えています。
むしろ、SEO・AI・データ構造の3領域を横断的に理解している専門家でなければ成果が出しにくいのが実情です。
6. 相談・外部委託のタイミング:自社でやるか、プロに頼むか?
とは?Webマーケティングを劇的に変えるAI時代の【必須スキル】を徹底解説!6-scaled.webp)
自社で対応すべき範囲
-
コンテンツの一次情報収集
-
自社の強み・ブランドメッセージの整理
-
基本的なSEO・構造化の実装
外部に相談した方がよい範囲
-
トピックマップ設計(AIが理解する階層設計)
-
LLM向けコンテンツ構造の最適化
-
ChatGPT・Gemini など生成AI向けテストと評価分析
-
継続的なLLMO効果検証・改善
つまり、
「自社で作ったコンテンツをAIに伝わる形に翻訳してもらう」
という発想が現実的です。
専門家の知見を取り入れることで、最小コストで最大成果を得られる可能性が高まります。
7. まとめ:AI時代の“新しいSEO”=LLMOを理解しよう
とは?Webマーケティングを劇的に変えるAI時代の【必須スキル】を徹底解説!7-scaled.webp)
-
LLMOとは? → AIに理解・引用されるよう最適化する新時代のSEO
-
なぜ重要? → 検索結果がAI生成型(SGE)に変化しているから
-
どう進める? → 構造・根拠・信頼性・検証をセットで行う
-
難しさは? → AI評価軸が複雑で、専門的知見が必要
つまり、LLMOは単なる「SEOの次の流行」ではなく、
“AIと共存するマーケティング”の基盤技術です。
FAQ(よくある質問)
Q1:LLMOはSEOの代わりになるの?
→ いいえ、SEOの進化形です。SEOで得た基盤を活かしつつ、AI理解を追加する考え方です。
Q2:無料でLLMOを学べるサイトはある?
→ 海外ではGoogle Research BlogやOpenAI Developer Blogが参考になります。日本語資料はまだ少ないのが現状です。
Q3:LLMO対策はどんな業種に向いている?
→ 特にBtoB、専門分野(医療・金融・教育など)ではAIが内容精査するため、効果が出やすいです。
Q4:どのくらいの期間で成果が出る?
→ 構造と信頼性を整えるだけで3〜6ヶ月でAI引用率が上がる事例があります。
Q5:専門会社に相談するタイミングは?
→ 自社のSEOが頭打ちになった時点、またはAI検索で自社が引用されていないと気づいた時がベストです。
🔗 参考リンク:
Google Research Blog|Large Language Modelsの進化
経済産業省|AI人材育成・活用戦略2024
✅ 結論:自分でやりたい。でも難しい。だから相談する。
LLMOは、確かに「自分でもやってみたい」と思えるテーマです。
しかし実際には、AI評価・構造設計・データ連携のすべてを理解しなければ成果が出ません。
一歩踏み出したい担当者こそ、
「まずはプロに相談して、正しい方向性をつかむ」
ことが成功への近道です。
AI時代のWebマーケティングは、「知識」よりも「戦略と実装」がものを言います。
あなたの企業のLLMO戦略も、今から動き出す価値があります。
企業様からのWEBマーケティング・コンサルティングに関するお問い合わせやご質問をお待ちしております。初回相談は無料で対応しており、お電話やzoomなどで対応いたします。費用面なども含め、お気軽にお問い合わせ下さい。その他、広告運用代行やWeb制作なども併せて受け付けております。

とは?-Webマーケティングを劇的に変えるAI時代の【必須スキル】を徹底解説!.png)