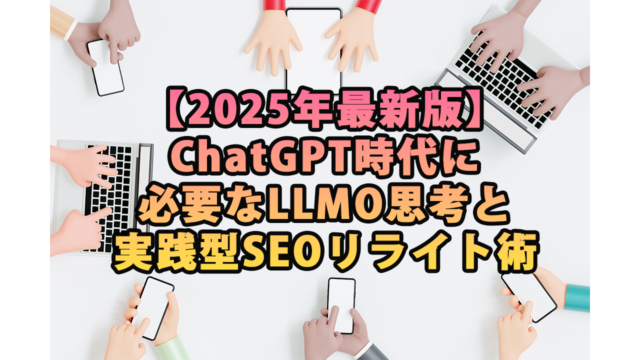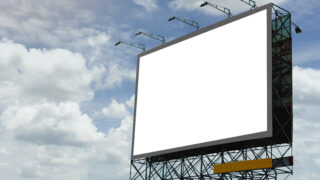LLMO(Large Language Model Optimization)は、大規模言語モデル、例えばChatGPTなどのAIが出力する回答において、自社の情報やブランド名が優先的に表示されるようにするための最適化施策です。
最近では、従来の検索エンジンに加えて、AIによる自然言語応答を通じて情報を得るユーザーが増加傾向にあります。
特にGoogleでは、「AI Overview」と呼ばれるAI生成の回答が検索結果の上部に表示されるケースが増えており、従来のSEOやリスティング広告以上にユーザー接点としての重要性が高まっています。
そのため、AIが提示する情報の中に、自社サービスやWebサイトが引用されるように働きかける必要が出てきています。これがまさに、LLMOという考え方が注目される理由です。
ただし、LLMOはまだ新しい概念であり、標準化された実践方法や具体的な成果の測定については今後の研究・実証が求められる段階です。
このページの目次
大規模言語モデル(LLM)の概要
LLM(Large Language Model)は、膨大なテキストデータを基に訓練され、人間のような自然な言語を生成したり、理解したりできるAI技術です。
この技術によって、文章の自動生成や質問応答、要約、翻訳などが可能となり、従来のアルゴリズムでは実現が難しかった高度な言語処理を実現しています。
代表的な大規模言語モデルには、OpenAIの「ChatGPT」やGoogleの「Gemini(旧Bard)」などがあります。
ただし、これらのモデルは訓練データの中に含まれる誤情報をそのまま出力することがあるため(いわゆる“ハルシネーション”)、実際に活用する際には内容の検証を行う姿勢が求められます。
なぜ今、LLMO対策が注目されているのか?
近年、ユーザーの情報収集手段として、AIを活用した検索行動が日常化しつつあります。これが、LLMO(Large Language Model Optimization)対策が重視されるようになった大きな理由のひとつです。 中でも話題となっているのが、Googleが2024年に導入した「AI Overview」です。この機能は、検索キーワードに対してAIが自動で要約・解説を行い、通常の検索結果よりも上位にその回答が表示されるという仕組みになっています。
Google Japan Blogによれば、2025年5月21日時点で、AI Overviewは世界中で15億人以上のユーザーに活用されており、すでに200以上の国や地域に展開されています。この技術の登場により、従来の検索順位よりもAIによる回答がユーザーの目に触れやすくなっているのが現状です。
また、AI Overviewを利用しているユーザーの多くは、検索体験に満足しているとされており、検索の回数自体も増加傾向にあることが報告されています。
昨年の発表以来、AI による概要は 15 億人以上のユーザーに活用されており、現在では 200 の国と地域で提供しています。AI による概要のユーザーは検索結果に満足し、検索の頻度も増加しています。
昨年の発表以来、AI による概要は 15 億人以上のユーザーに活用されており、現在では 200 の国と地域で提供しています。AI による概要のユーザーは検索結果に満足し、検索の頻度も増加しています。引用:Google Japan Blog
このような変化に伴い、商品比較や購入検討、サービス選定といった場面でも、生成AIを活用するユーザーが着実に増加しています。
実際に、Attestの調査によると、全体の約47%の消費者が「生成AIを使って購買前にリサーチする可能性が高い」と回答していることが明らかになっています。
つまり、現在のデジタル環境では、AIによる検索結果に企業名やブランド名が含まれていないと、本来接点を持てたはずの見込み顧客を逃してしまうリスクが高まっているというわけです。
こうした状況から、多くの企業が、AIによる回答に自社に関する情報を組み込ませることを目的とした「LLMO対策」に本格的に取り組み始めています。
以下、実際に弊社クライアント、おかもと弓削整骨院でのgoogle検索におけるLLMO事例です。

以下が、同じく、弊社クライアント「クラッセ歯科」様のchatgptでの検索結果です。

LLMO対策とSEOの相違点
LLMOとSEOは何が違うのか? LLMOとSEOはいずれも検索行動に対する戦略ではありますが、アプローチの方向性は大きく異なります。 LLMO対策は、ChatGPTのような生成AIに自社のデータやブランド情報が自然に引用されるように工夫する取り組みです。
一方で、SEO(検索エンジン最適化)は、Googleなどの検索エンジン上で特定のキーワードにおいて自社サイトを上位に表示させるための技術的・コンテンツ的な施策を意味します。 つまり、SEOは従来の検索結果の“順位”に注目しているのに対し、LLMOは“AIが何を根拠として回答を生成するか”に焦点を当てた対策といえるでしょう。
| 項目 | LLMO | SEO |
|---|---|---|
| 目的 | AIに自社の情報を正しく認識・引用させ、回答に出典リンクを掲載させること | 検索結果で上位表示され、ユーザーにクリックされてサイト訪問につなげること |
| 対策対象 | 大規模言語モデルを用いるAI(ChatGPT、Perplexity、Geminiなど) | 検索エンジン(Google、Yahoo! など) |
| 掲載される場所 | AI検索の回答画面(回答の一部や引用リンクとして表示される) | 検索エンジンの検索結果ページ(スニペットやサイトリンクとして表示される) |
| 検索トリガー | ユーザーがAIチャットボットに質問やリクエストを入力する | ユーザーが検索エンジンにキーワードを入力して検索を実行する |
| 掲載までのフロー | クロール→学習→回答生成 | クロール→インデックス→順位付け |
| ユーザー行動 | 自然言語で検索→回答を確認→参考/引用リンク先へ遷移(任意) | キーワードで検索→検索結果を確認→各サイトへ遷移→コンテンツを確認 |
| 効果測定指標 | ・回答内でのリンク表示回数 ・各AIサービスからの流入数 |
・検索順位 ・セッション数 ・CV数など |
| 運用上の主な手法 | llms.txtの作成・設置、独自データ・一次情報の追加、サイトや情報の権威性・信頼性を高める、構造化マークアップの実施 | サイト内部の最適化、被リンク獲得、検索意図を満たすコンテンツの作成、EEAT対策 |
GEOやAIOとの違い
現在、LLMO以外にも似たような概念を表す用語が複数あります。
混同しやすいので、ここで整理しておきましょう。
<LLMOに似た用語の意味>
| 用語 | 正式名称 | 概要 |
|---|---|---|
| GEO | Generative Engine Optimization | 「生成エンジン最適化」と訳され、LLMOとほぼ同じ意味で使われることが多い。 生成AIエンジンとその回答ロジックに対する最適化を指し、AIがWeb検索を通じて情報を探す際に、自サイトが引用されるよう最適化することを目指す。 |
| AIO | AI Optimization | 「AI最適化」と訳され、LLMOやGEOを包含するより広い概念。 生成AIだけでなく、検索、レコメンドなど、あらゆるAIに対する最適化の総称として使われる。 |
| AEO | Answer Engine Optimization | 「回答エンジン最適化」と訳され、AIが生成する「回答」そのものに焦点を当てた最適化を指す。 質問に対する直接的な回答を提供するAIシステムに最適化することが特徴。 |
LLMO時代の到来で、検索体験はどう変わるのか?
AIによる検索が一般化することで、ユーザーの情報収集スタイルにも大きな変化が訪れようとしています。その最たるものが、「Webサイトを訪れず、AIの回答だけで満足してしまう」という行動パターンです。 従来の検索プロセスでは、ユーザーはGoogleやYahooなどの検索ボックスにキーワードを入力し、表示されたリンク先のWebページを開いて、必要な情報を得ていました。
しかし、生成AIが主役になる新たな検索体験では、検索結果に表示されるAIによる要約や回答だけで目的を達成し、そのまま検索を終えるケースが増えています。 このような「クリックされない検索」の傾向は、「ゼロクリック検索(Zero-click Search)」と呼ばれており、AIが提供する回答の精度が高まるほど、Webサイトへの遷移が減少する可能性があるのです。
AI Overviewの影響と、ゼロクリック検索に対する懸念
ahrefsblogの分析によれば、AI Overviewが表示される検索キーワードでは、従来の検索結果と比較して上位ページの平均クリック率(CTR)が約34.5%も低下するというデータが報告されています。 つまり、AIによる要約や回答が検索画面の最上部に表示されることで、ユーザーがリンクをクリックせずに検索行動を終えるケースが増えている可能性があります。
とはいえ、2025年7月時点では、ゼロクリック検索によるWebサイト訪問数の大幅な減少が実際に起きているかどうかについては、明確な結論が出ていません。この分野ではデータにばらつきがあり、専門家の意見も分かれているのが現状です。 たとえば、メディア分析プラットフォーム「Chartbeat」で研究員を務めるシンシア・ブー氏は、世界中の4,000以上のWebメディアを対象としたトラフィックの動向を分析した結果、2025年に入って以降もGoogle検索やDiscoverからの訪問者数に目立った変化は確認できていないと述べています。
しかし、仮にゼロクリック検索が今後さらに進行した場合、多くのユーザーは「サービス名」や「ブランド名」を明確に入力して直接的に企業サイトを訪れる「指名検索」に行動をシフトさせると考えられます。 このような状況では、従来のSEOだけでは検索市場を網羅するのが難しくなります。
SEO施策のみでは、AIが主導する検索環境で情報接点を確保し続けることは困難であり、ユーザーの関心を逃してしまうリスクがあるのです。 そこで必要となるのが、AIによる回答領域に自社の情報を的確に反映させる「LLMO対策」です。検索というフィールドが変化する中で、AIに適切に取り上げられる工夫が、今後のデジタル戦略において不可欠となっていくでしょう。
LLMの仕組みとLLMO対策の基本的な方針
LLMが学習から回答を出力するまでの流れは、大まかに分けると以下の通りです。
1,膨大なテキストデータから言語のルールを学習

生成AIが自然な言語を操れるようになるまでには、いくつかの重要な学習ステップがあります。最初の段階は、人間の言葉を扱えるようにするための“土台作り”です。 人間が文を読むようなかたちでAIがテキストを理解するわけではありません。まずは、大量の文章データを単語やその一部(トークン)に細かく分け、それらをAIが計算処理できる数値のかたちに変換する工程が行われます。
この数値化されたデータを使って、AIは言葉の並び方や意味のつながりをパターンとして学習していきます。たとえば「Aという単語のあとにはBが続きやすい」といった確率的な関係性を数百万、数億の例から見つけ出すことで、文法や表現のクセ、あるいは一般常識に近い知識を徐々に獲得していくのです。
特に、「よくある質問とその答え」のように規則性のある形式や、同じ専門用語が繰り返し登場するような文章は、AIにとって非常に学習しやすいとされています。 さらに、用語解説をまとめたり、段落を分けて情報を整理するなど、「構造化された情報」を提示する工夫も、AIに効率よく理解させる手助けになります。こうした書き方は、AIによる理解を促進するうえで非常に有効な方法です。
LLMに引用されやすいサイトを目指すには?
AIに自社の情報を取り上げてもらうためには、単に情報を載せるだけでなく、「AIが理解・学習しやすい形式」で提供することが重要です。以下は、LLMに認識されやすいコンテンツを設計するための代表的な工夫です。
-
FAQ形式など、一定のパターンに沿った表現を活用すること
質問と回答が明確に分かれた定型的な文構造は、AIにとって意味の理解やパターン抽出がしやすいため、情報源として有利に働きます。 -
専門用語やキーワードの反復使用
特定のワードが複数回登場することで、AIにとって「このページはその話題に特化している」と認識されやすくなります。 -
関連語や同義語も組み合わせて使用
同じテーマに関連する語彙を網羅することで、文脈の広がりが生まれ、AIがテーマを理解しやすくなります。 -
用語解説や補足説明を設ける
初めてその情報に触れる人にもわかるような用語の解説セクションがあると、AIも内容の位置づけを把握しやすくなります。
人間の基準に合わせて回答の品質を調整

AIがより自然で正確な回答を生成できるようにするには、人間の判断基準を取り入れた「品質調整」のプロセスが欠かせません。この工程では、AIが人間らしい言語感覚に沿った応答を返せるよう、追加学習やフィードバックの仕組みが使われます。 代表的な手法には次の2つがあります。
ファインチューニング(微調整) 優れた応答の事例や専門性の高いコンテンツなどをAIに再学習させ、望ましい出力傾向を強化します。 RLHF(人間のフィードバックを活用した強化学習) AIが生成した複数の応答を人間が評価し、「どの回答がより好ましいか」を判断してフィードバックを返すことで、AIはより良い返答の方向性を学びます。
こうしたプロセスを経て、AIは以下のような人間が重視する評価軸に基づいた判断力を備えていきます。 情報の正確性(誤情報を避ける) 内容の透明性(出典や根拠が明示されているか) 論理性と一貫性(矛盾のない文章かどうか) この段階で、AIは信頼できる情報源を選別するスキルも高まっていくため、自社のWebサイトが「信頼されるソース」として認識されることが、引用されるための重要な条件となるのです。
問いに応じて知識を組み合わせ応答
言語の構造を理解し、応答品質を高める訓練を積んだAIは、いよいよユーザーの具体的な問いかけに対して返答を作る段階へと進みます。 プロンプト(質問や指示)が入力されると、AIはまずその背後にある意図や文脈を読み取ろうとします。その上で、事前に学習した知識に加えて、必要に応じて外部の情報を参照します。この際に使われる技術のひとつが、Retrieval-Augmented Generation(RAG)です。
RAGでは、AIが関連性の高いドキュメントやWeb情報をリアルタイムに検索・取得し、それを参考にしながら応答を構築します。 集めた情報の中から、質問内容に最も適したキーワードやフレーズを選び出し、それらを論理的に組み立てて、自然な応答文を生成します。特に、キーワードとの関連性が高い情報や、表・リストのように整理された形式のコンテンツ、出典や更新日が記載された信頼性のある情報は、AIが参照しやすい傾向にあります。 応答が完成した後は、内容に問題がないかをチェックする工程が入ります。差別的な表現や誤情報、不適切な内容が含まれていないかどうかを、AI自身または外部のフィルタリングシステムが確認し、そのうえでユーザーに回答が提供されます。
AIに取り上げられやすいサイトの特徴
こうしたAIの応答生成プロセスを踏まえると、「AIに引用されやすいWebサイト」にはいくつかの共通点があります。情報構造や信頼性の観点から、以下のような工夫が有効です。
・ページ冒頭でテーマや主張を明示している
AIはページを全て読むわけではなく、冒頭から意味を汲み取るため、主題をはっきり書くことが重要です。
・表や箇条書きを活用して、情報を視覚的に整理している
構造化された情報は、AIが要点をつかみやすく、引用に適していると判断されやすくなります。
・要点をリスト形式で明示している
箇条書きやセクション見出しでまとめられた内容は、AIが文脈を認識しやすく、回答文に反映されやすくなります。
・公開日・更新日・出典などのメタ情報を記載している
「情報がいつ、どのような根拠で書かれたか」を示す要素は、信頼性の指標としてAIが重視するポイントです。
LLMO対策の具体的な施策を解説
LLMO対策における施策を、短期ですぐに取り組むべき施策と、中長期にわたって取り組むべき施策に分けて解説します。
短期で取り組むべき施策
短期で今すぐ取り組むべき施策として、以下が挙げられます。
| 項目 | 詳細 | 目的 |
|---|---|---|
| Googleビジネスプロフィール登録 | 会社名でのGoogleビジネスプロフィールの作成 | エンティティをLLM(主にGeminiやAI Overview)に認識させる |
| llms.txtファイルの設置 | ルートディレクトリにllms.txtを設置する | LLMがサイトの構造や情報を利用する補助をする |
| robots.txtのAIクローラーへの対応 | robots.txtファイルでAIクローラーへクロール可否を示す | AIクローラーによるサーバーへの負荷を和らげる |
| 構造化マークアップの実装 | コーポレートサイトTopページには「Organization」などの、各ページに合った構造化マークアップの実装 ※参考:Google検索セントラル |
LLMがサイト内の情報を正しく利用できるようになる補助をする |
| Aboutページの作成 | 自社やサービスに関する情報を掲載するAboutページを作成する | LLMが自社情報を正確に認識できるようにする |
これまでにご紹介した施策は、まさに今すぐにでも着手すべき「LLMO対策の土台づくり」と言える重要なステップです。これらの対応は、大規模言語モデル(LLM)がWebサイト上の情報を的確に把握・理解するための環境を整える役割を担っています。 どれほど多くのコンテンツを追加しても、情報の構造や見せ方に配慮されていなければ、AIがその内容を正確に認識できない可能性があります。
つまり、せっかくのコンテンツ資産も、適切に活用されないまま埋もれてしまうリスクがあるのです。 だからこそ、まずは基本的な整備を徹底し、LLMが情報を読み取りやすい状態を構築することが不可欠です。その上で、中長期的な視点に立ったコンテンツ戦略やブランディング施策に取り組むことを、私たちは強くおすすめしています。
中長期で取り組むべき施策
中長期で取り組むべき施策は、その目的や対策したいLLMに応じて以下3種に分けることができます。
| 項目 | 対応LLM | 目的 |
|---|---|---|
| サイト全体のLLMO対策 | ・ChatGPT ・Gemini ・Perplexity ・AI Overview |
「サイト全体の権威性」や「ブランドやサイトとのトピックとの関連性」を高め、サイト全体でLLMに引用されやすいようにする |
| 比較文脈メインのLLMO対策 | ・ChatGPT ・Gemini ・Perplexity ・AI Overview |
主に比較文脈(例:おすすめの〇〇を教えてください)の質問で、自社のブランドやサイトの言及を強化する |
| AI Overview特化のLLMO対策 | ・AI Overview | 主にGoogle検索のAI Overview等にリンク付きで掲載されることを目指す |
基本的な方針としては、Web上での情報発信量を戦略的に増やしていくことが中心となります。大規模言語モデル(LLM)は、インターネット上に存在する膨大なデータをもとに知識を獲得・蓄積していくため、自社に関する情報を多く公開することで、AIの応答内に取り上げられる可能性が高まります。
これが、LLMO施策の最も基本的かつ重要な目的のひとつです。 また、この取り組みは、Googleが評価指標として重視する「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」の観点からも有効な対策となります。AIは、信頼できると判断された情報源を優先的に引用する傾向があると考えられるため、外部からの被リンク獲得や、信頼性の高いメディア・業界サイトなどへの掲載が今後ますます重要になっていくでしょう。
サイト全体のLLMO対策
サイト全体のLLMO対策は、サイト全体で権威性やトピックとの関連性を高め、情報がLLMに引用されやすいよう最適化していく施策です。
サイト全体のLLMO対策は、以下の項目があります。
| 項目 | 詳細 | 目的 |
|---|---|---|
| 被リンク獲得 | 権威性や関連性が高いサイトの被リンクを獲得する | 権威性が高いページほどはLLMの回答作成に利用されやすい傾向があると考えられるため、権威性の向上を目指す |
| プレスリリース含むPR施策の実施 | プレスリリースを例としたPR施策を実施する | LLMの学習元となるWeb上の自社に関する言及量を増やし、自社とトピックの関連性を強化する |
| 業界の権威あるWeb媒体での露出 | 権威・信頼性のあるWeb媒体で特集記事を作成してもらう | 自社のWeb上での言及数を増やすとともに、権威性・信頼性の向上を図る |
| Youtube・SNSでの露出 | 関連するYoutubeチャンネルやSNSアカウントで取り上げてもらう | LLMの学習元となる自社に関するWeb上の言及数を増やし、自社とトピックの紐づけを強化する |
比較文脈メインのLLMO対策
比較文脈メインのLLMO対策は、「おすすめの〇〇(商品・サービスなど)を教えて」などといった質問へのLLMによる回答に、自社情報が表示されるようにするための施策です。
比較文脈メインのLLMO対策には、以下の項目があります。
| 項目 | 詳細 | 目的 |
|---|---|---|
| 比較記事の作成 | 自社で「〇〇 おすすめ」といったキーワードでの比較記事を作成 | LLMの学習元となる比較記事を作成し、自社とトピックの関連性を強化を図る |
| 他社比較記事での掲載情報の監視 | 他社の「〇〇 おすすめ」といったキーワードの記事で、自社のサービス・製品情報が正しく掲載されているか定期的に確認・修正依頼 | LLMの学習元となる競合比較記事に、自社情報が正しく掲載されることで、自社とトピックの関連性強化を目指す |
AI Overview特化のLLMO対策
AI Overview特化の対策は、現状特にLLMO対策のインパクトが大きいと考えられるAI Overviewに特化し、AI Overview内に自社の情報・リンクが表示されるようにするための対策です。
AI Overview特化の対策には、以下の項目があります。
| 項目 | 詳細 | 目的 |
|---|---|---|
| FAQコンテンツの作成 | 「よくある質問」や「Q&A」といったFAQコンテンツを制作する | LLMが理解しやすいと考えられる形式のコンテンツを制作し、自社の発信した情報がLLMに取り上げられることを目指す |
| ページ単位で信頼性のある情報を用いたコンテンツ作成 | 裏付けのとれた情報と情報源への発リンクをコンテンツに含め、信頼性を向上させる | 信頼性の高い情報を掲載しているサイトをLLM(特にAI Overview)は取り上げる傾向があると想定できるため、信頼性向上を図る |
| ページ単位でLLMが認識しやすいコンテンツの作成 | 表や箇条書きといった構造化されたコンテンツを作成する | LLMは表や箇条書き等のコンテンツを利用しやすいとされており、それらを含めたコンテンツを制作することで、自社発信の情報がLLMに取り上げられることを目指す |
| 対策したいトピックに関連するページ作成とSEO対策を実施する | トピックに関連するページが検索上位に表示されるよう、ページ作成及びSEO対策を行う | LLM(特にAI Overview)は検索上位のページを要約元・参照元とする傾向があると考えられるため、ページ単位で検索上位を目指す |
LLMOのメリット
基本的な方針としては、Web上での情報発信量を戦略的に増やしていくことが中心となります。大規模言語モデル(LLM)は、インターネット上に存在する膨大なデータをもとに知識を獲得・蓄積していくため、自社に関する情報を多く公開することで、AIの応答内に取り上げられる可能性が高まります。これが、LLMO施策の最も基本的かつ重要な目的のひとつです。
また、この取り組みは、Googleが評価指標として重視する「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」の観点からも有効な対策となります。AIは、信頼できると判断された情報源を優先的に引用する傾向があると考えられるため、信頼性を裏付ける施策――たとえば外部からの被リンク獲得や、信頼性の高いメディア・業界サイトなどへの掲載――が今後ますます重要になっていくでしょう。
従来のSEOでは届かなかった層に情報を届ける、新たな可能性 LLMO(大規模言語モデル最適化)を取り入れることで、従来の検索エンジン最適化(SEO)だけでは接点を持てなかったユーザー層へのアプローチが可能になります。
近年、ChatGPTをはじめとした生成AIの普及により、情報の探し方はますます多様化しています。特に、Googleが提供する「AI Overview」などの機能を通じて、ユーザーは従来のキーワード検索に加え、より曖昧で抽象的な悩みや質問を“自然な文章”で入力し、AIからの回答を求める傾向が強まっています。
こうした場面で、自社の製品やサービスがAIによる回答内でソリューションとして紹介されれば、ニーズが顕在化していない潜在層にも自然にリーチすることが可能です。 さらに、LLMO対策を行うことで、AIが自社サイトを情報の出典としてリンク表示する機会が増加し、これまでの検索チャネルとは異なる形で集客の入り口を広げる効果が期待できます。 実際、弊社でも「ChatGPTの回答で貴社を知り、問い合わせを決めた」というケースが確認されており、LLMOが新たな集客導線として機能し始めていることが実感されています。
先手を打つことで得られる“LLMOの先行者優位性”
LLMOは、まだ市場全体では新しい概念であり、本格的に対策を講じている企業はごくわずかです。この黎明期に対応を進めておくことで、他社に先んじてAI内での認知や可視性を高めるチャンスが広がります。 いわゆる“先行者利益”とは、新たな市場や技術領域にいち早く参入した企業が、後発の競合に対して有利なポジションを確保できる戦略的優位のことを指します。
現時点では、AIによる回答に引用される情報源はまだ限られているため、先にLLMO対策を施した企業の情報が、AI内での引用率を高め、結果的に競合の露出を抑えるという副次的効果も見込めます。
ただし、LLMOは既存のSEO戦略を否定するものではなく、検索エンジン最適化を補完する位置づけの施策です。両者を並行して実施することで、従来型検索とAI検索の双方に対応した、多角的な集客戦略が可能になります。 従来のSEO施策と連動しやすく、取り組みやすいLLMO対策 LLMO対策は、多くの部分で既存のSEO施策と親和性が高いため、導入のハードルが比較的低いのが特徴です。
被リンク獲得やユーザーに価値を提供するコンテンツ作成は、これまでのSEOにおいても重要視されてきた要素であり、これらを継続的に実施していくことで、LLMO対策においても良い成果を期待できます。 自社でLLMOを進める場合、既にSEOやWeb担当者がいる場合は、比較的スムーズに対策を始められることが多く、迅速な実行が可能です。
ただし、LLMO対策にはSEOのより高度な知識やノウハウを要するケースもあるため、専門的な担当者が不足している場合は、外部の専門会社に依頼することも選択肢として検討すべきでしょう。 検索順位に左右されず、ユーザーへの露出機会を拡大 LLMOのメリットとして、従来のSEOで検索結果の上位に表示されていない場合でも、LLMを通じて自社情報がユーザーに届く可能性がある点が挙げられます。
従来の検索では、上位表示ページが大半のトラフィックを集めるため、下位にあるサイトはユーザーの目に触れる機会が限られていました。 一方で、LLMO対策を施すことで、AIによる質問回答内に自社の製品・サービス情報が掲載されると、順位に関係なく露出を獲得できるのです。
固有名詞での検索を増やす効果も期待できる
なお、AI Overviewのような一部の大規模言語モデルは、依然として検索上位のページを参照し要約する傾向もあるため、従来のSEOを軽視するのは危険である点にも注意が必要です。 ブランド名での指名検索増加にもつながる さらに、LLMO対策を実施することで、ユーザーがAI回答をきっかけに自社ブランドに興味を持ち、固有名詞での検索を増やす効果も期待できます。
例えば、「LLMO対策をしたい」という質問に対して、弊社「株式会社linkwin」の名前がAI回答に登場すれば、その後にユーザーが「株式会社linkwin」といった指名検索を行う可能性が高まります。
LLMごとに異なる対策が必要な理由
LLMO対策は、利用する大規模言語モデル(LLM)の種類によって内容や手法が異なる点が特徴です。現在、さまざまなLLMが登場していますが、それぞれ回答の生成方法や出力形式に違いがあるため、対策もカスタマイズが求められます。
主なLLMの例
ChatGPT(GPT-4、o1、o3など)
Gemini(2.5 Pro、2.0 Flashなど)
AI Overview(AIモード)
Perplexity(Pro Search、Deep Researchなど)
例えば、OpenAI社が独自開発したChatGPTは「クローズドAI」と呼ばれるモデルで、回答内にウェブリンクが表示されることはあまりありません。 対して、Perplexityは「Retrieval-Augmented Generation(RAG)」に分類されるモデルで、インターネット上の情報をリアルタイムに検索・収集し、回答の中で参照したサイトへのリンクを示す特徴があります。
このような違いを踏まえ、各LLMの特性に合わせて最適なLLMO対策を検討することが重要です。 そのため、ChatGPTに対しては、回答内で自社名やブランド名が固有名詞として確実に言及されるような施策が求められます。
一方で、Perplexityのようなモデルには、回答時に自社が発信した情報が明確に表示されるよう対策を講じる必要があります。 しかし、2025年7月時点においては、ChatGPTとGeminiへの対応を優先的に進めることが現実的です。これは、これら二つのAIが市場におけるシェアが特に大きいためです。
FirstPageSageの調査によると、米国での主要な生成AIチャットボットの市場シェアはChatGPTが約60.6%を占めています。また、Google Japan Blogの発表によれば、GoogleのAI Overviewは世界で約15億人のユーザーに利用されているとのことです。 どちらのモデルを重点的に対策するかは、自社のビジネス形態によって判断すると良いでしょう。
消費者向けサービス(ToC)を展開している場合は、幅広いユーザーにリーチ可能なAI Overviewを優先的に強化することが推奨されます。 対して、企業間取引(ToB)に注力している場合は、比較的リテラシーの高い意思決定者が利用すると考えられるChatGPTの対策も視野に入れ、両者をバランスよく進めるのが望ましいです。
成果の測定手法がまだ確立されていない
LLMO対策の現状の課題として、効果検証のための標準的な成果測定方法がまだ確立されていないことが挙げられます。 2025年に入ってから急速に注目されるようになった施策であるため、対応策や評価指標はまだ発展途上にあります。
現在、日本語対応の成果測定ツールもいくつか登場していますが、今後さらに多様なツールや効果測定のフレームワークが登場することが期待されています。
LLMO対策は継続的かつ中長期的な取り組みが必要
LLMO対策には、短期間で成果を得ることが難しいという側面がある点もデメリットの一つです。 この対策の根幹は、LLMに自社や自社の情報を正しく認識させることにあります。そのためには、自社に関するWeb上の情報量を増やす必要がありますが、この情報拡充は一朝一夕には達成できません。 そのため、継続的な広報活動を通じて、自社サイトのみならず複数のメディアやSNSなどでの露出を積み重ねていくことが欠かせません。
さらに、一部のLLMでは「カットオフ」と呼ばれる、学習データの収集時点が一定期間で区切られている仕組みを採用しているため、直近に対策を施しても、その成果をモデルが反映するまで一定のタイムラグが発生することがあります。 以上の理由から、LLMO対策は短期的な施策にとどまらず、長期的な視点で地道に取り組み続けるべきものであると言えるでしょう。
LLMO対策における注意点
SEO対策との両立が不可欠 LLMO対策を進める際には、従来のSEO施策と並行して取り組むことが非常に重要です。
AIを活用した検索技術が普及しても、SEOとLLMOは対立するものではなく、むしろ共存しながら補完し合う関係にあります。したがって、SEOの役割が急に薄れることは考えにくいでしょう。
また、LLMOが注目されているとはいえ、効果的な成果を得るためにはSEO対策も欠かせません。実際に、AIによる回答にブランドが登場する頻度と、そのブランドのSEOでの順位には強い関連性が指摘されています。 このため、SEOをおろそかにしてしまうと、LLMO施策による効果を最大限に引き出すのが難しくなる可能性が高いと言えます。
まとめ
LLMOは、AI検索の普及に伴い注目されるようになった、新しい最適化の考え方です。 ユーザーがより具体的な疑問や条件を直接AIに投げかける時代に入り、その細やかなニーズに応える情報をWeb上でどれだけ充実させられるかが、企業の競争力に大きく影響を与えるようになっています。
これに伴い、マーケティング戦略も「AIに選ばれるWebサイトを育てる」という視点で見直すことが、今後の情報発信や集客における重要なポイントとなるでしょう。 急速に変化するAI時代の検索環境に対応するため、いまこそLLMOを意識した情報設計やコンテンツ戦略に着手するタイミングです。
linkwinでは、そうした「AIに選ばれる状態」の実現を支援する「LLMOコンサルティングサービス」を開始しております。 「AI Overviewや生成AIの影響でアクセスが減少した」「早期にLLMO対策を進めたい」といったお悩みがございましたら、無料相談も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
企業様からのWEBマーケティング・コンサルティングに関するお問い合わせやご質問をお待ちしております。初回相談は無料で対応しており、お電話やzoomなどで対応いたします。費用面なども含め、お気軽にお問い合わせ下さい。その他、広告運用代行やWeb制作なども併せて受け付けております。